”収束進化”って?気になる言葉を調べてみた
- 知識BOX 生き物
- 2021年1月31日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年9月11日

よく聞く「進化」という言葉の中でも不思議な言葉「収束進化」。
進化の過程を知りたい人には必見です。
|収束進化とは?
”収束進化”とは、”収斂進化(しゅうれんしんか)”とも言い、複数の異なる系統の生物が、同様の生態的地位についたとき類似した形質を獲得する現象のことを指します。
「収斂進化」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より
2021年1月3日 (日) 05:00 UTC
よく言われているのは魚類である「サメ」と哺乳類である「イルカ」の類似性。どちらも水中をすばやく泳ぎ回るために進化した結果、とてもよく似た姿をしています。しかし、元となる骨格や器官、遺伝子が異なるため、別の系統に分類されます。
それでは、収束進化には他にどういった特徴があるのでしょうか。
|収束進化する有袋類と哺乳類
オーストラリア大陸に暮らす有袋類は、それ以外の大陸に住む哺乳類との収束進化が多いのが特徴です。
代表的なものは有袋類である「フクロモモンガ」とリスの仲間である「モモンガ」や、「フクロアリクイ」と「アリクイ」。哺乳類のほうが早く名前のついてものが多く、有袋類に「フクロ」とつけることで区別しています。
なぜオーストラリア大陸と他の大陸で収束進化が進んでいるかというと、他の大陸では哺乳類が暮らしていた環境に有袋類が進出することができたからです。似た環境が似た姿を作り出す、とても分かりやすい例になっています。
|「イルカ」も「サメ」も魚? 人間の認知について
ここで疑問に思うのが、違う遺伝子系統を持つ生き物たちを、なぜ私たちは「似ている」と感じるのでしょうか。
「イルカ」も「サメ」も、科学的には大きく異なった生き物です。
しかし室町時代には「クジラ」も「サメ」も「魚」と呼ばれていました。
違う生き物とされたのは、科学が発達したここ数百年の歴史であるということがわかります。
このことからわかるのは、人は科学の証明とはちがう「見た目の判断」でグループ分けをする本能を持っているということ。収束進化は、科学の発達がなければ見つからなかった現象かもしれません。
|”収束進化”のまとめ
sh~が持っているコウモリの専門書には、オオコウモリとショウコウモリは収束進化による別系統の遺伝子を持っているのではないかと書かれていました。今調べてみると、その説は否定されているようです。
まだまだ科学の証明と人の認知で変わってくる部分がありそうですね。
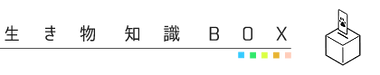
Comments